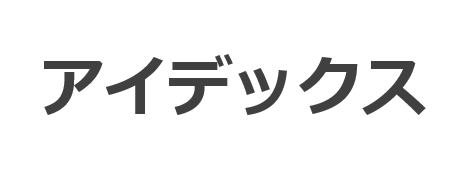「脱炭素経営という言葉はよく耳にするけれど、具体的に何を意味するのか?何をどのように取り組むのか?わからない…」 そのように感じている経営者の方は少なくありません。
また、脱炭素経営に「コストがかかる」という印象を持つ方もいますが、脱炭素経営はコスト削減や企業価値向上の手段であり、むしろ対応が遅れることの方が経営リスクになる時代になっています。
本記事では、脱炭素経営の「なぜ?何を?どうやって?」など、取り組むにあたってのはじめの一歩(ポイント)をお届けします。
脱炭素経営とは?
脱炭素経営とは、脱炭素(二酸化炭素排出量を実質ゼロにする取組)の視点を織り込んだ経営のことで、経営戦略として脱炭素に取り組むアプローチのことを指します。
具体的には、以下のような活動が含まれます。
- 使用エネルギーの削減(省エネ)
- 再生可能エネルギーの導入
- サプライチェーン全体での二酸化炭素排出量の削減
- 環境配慮型製品・サービスの開発
脱炭素経営に取り組むメリット
脱炭素経営に取り組むことで次のようなメリットが得られます。
コスト削減と収益性向上
エネルギー使用量や二酸化炭素排出量を可視化し、省エネ改善や高効率設備への更新を進めることで、光熱費・原材料費の削減につながります。
企業価値・ブランド向上
環境対応が進んでいる企業を選ぶ顧客や取引先が増えており、特に大手企業からは二酸化炭素排出量の算定を求められるケースもあります。
脱炭素に取り組む姿勢を示すことで、取引先や顧客、金融機関等からの評価が高まり、企業価値向上につながります。
人材の確保・定着
若い世代ほど環境への意識が高く、「環境への貢献」が企業選択のひとつの基準となっています。
脱炭素経営は採用活動の差別化要素となり、従業員のエンゲージメントや組織の魅力向上にもつながります。
新たなビジネスチャンス創出
脱炭素経営の取組は、省エネ製品や環境配慮型サービスの開発、地域の脱炭素プロジェクト参画など、新規事業のきっかけにもなります。
脱炭素経営に取り組まないリスク
逆に、脱炭素経営に取り組まないでいることのデメリットには、次のようなものが挙げられます。
競争力の低下
ESG・SDGs視点での企業評価が進むなか、脱炭素に取り組まない企業は、国内外の取引から外れるリスクもあります。
コスト負担の拡大
エネルギー価格の上昇やカーボンプライシングへの対応が遅れると、コスト負担が重くなります。
人材確保の難航
環境意識の高い若手や技能者から敬遠され、採用競争や離職防止で不利に陥るおそれがあります。
脱炭素経営の進め方
愛知県が発行している脱炭素経営ハンドブックでは、脱炭素経営の進め方が次のように整理されています。
ステップ1:知る
カーボンニュートラルに向けた潮流や国、県、市町村のカーボンニュートラルに関わる政策など、脱炭素経営に関する情報を収集するとともに、自社を取り巻く状況や今後の変化を見据え、脱炭素経営方針の検討を行います。
ステップ2:測る
自社のエネルギー使用量等の把握を行い、事業活動に伴う二酸化炭素排出量を算定します。
また、エネルギー使用量や二酸化炭素排出量の可視化や省エネ余地の把握など、主要なエネルギーの使用先や二酸化炭素排出源・排出量を分析し、削減対象と方法を検討します。
ステップ3:減らす
二酸化炭素排出量削減の目標を設定し、目標達成のための計画を策定します。
計画策定後は、年度毎・実施部門毎に計画実施状況を管理し、実施項目毎の排出量削減効果を確認。必要に応じて計画の見直しを行います。
まとめ
脱炭素経営は、経営改善と成長の手段となります。
取引条件・採用・企業価値など経営全方位に影響を与え、取り組まないことによるリスクも見逃せません。
国や自治体による制度をうまく活用し、脱炭素を経営に取り入れてみてはいかがでしょうか。